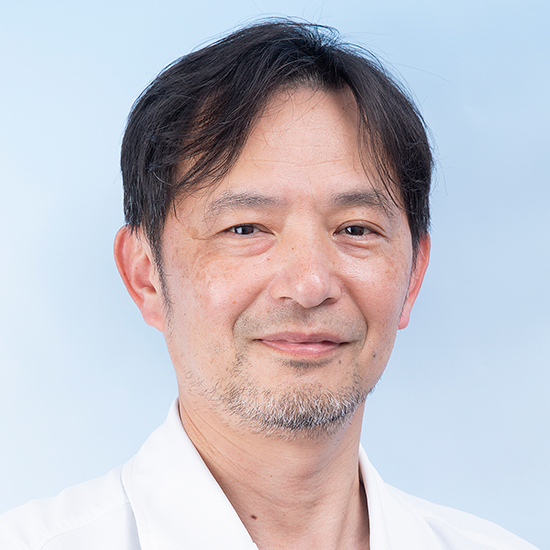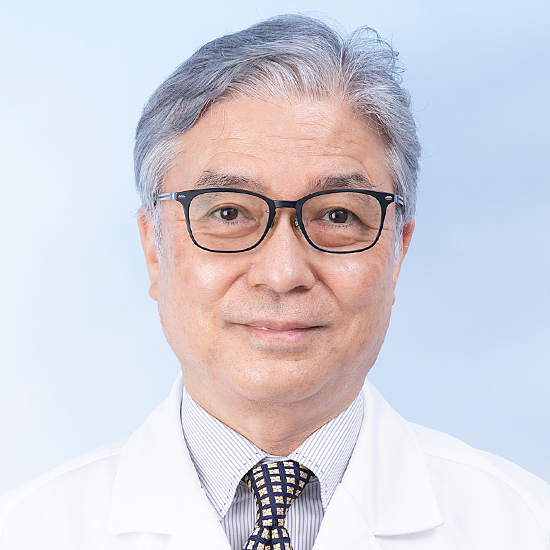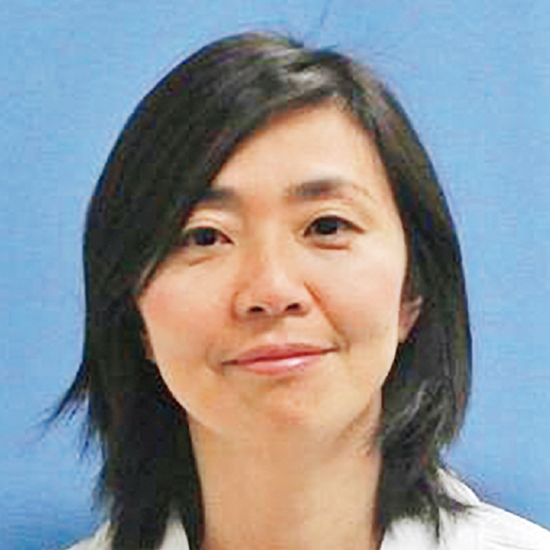リハビリテーション科

基本情報
特徴
高齢者の増加に対応した急性期リハビリテーションの実践
厚生労働省は「リハビリテーションのあり方」について、以下2つのモデルを提示しています。
- 脳卒中・骨折など突発完成型の疾患に対する治療モデル
- 安静状態が長く続くことで起きる疾患(廃用症候群)の治療モデル
いずれも、発症後早い時期からの重点的なリハビリテーションが望まれます。これに対応するため、当院では疾患別に提供体制を整備。地域医療とも連携しながら、急性期のリハビリテーションに力を注いでいます。
基本方針
- 急性期リハビリテーションを重点的に行う
- 廃用症候群を積極的に予防する
- 地域の医療・福祉機関とのスムーズな連携を図る
主な業務内容
疾患別にリハビリテーションチームを組織し、治療にあたっています。
脳卒中リハビリテーションチーム
脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などの脳血管疾患)では、疾患で起きる障害や治療上の安静によって、生活にさまざまな支障をきたします。当院では発症直後よりリハビリテーションを計画し、早期の離床を目指します。専門スタッフの細やかな支援で、急性期から安全にリハビリテーションへ取り組んでいただけます。 当院での治療後は地域のリハビリテーション専門病院と連携しながら、家庭や社会への復帰をサポートします。
運動器リハビリテーションチーム
早期の機能回復・社会復帰を目標に、主に整形外科の患者さんに対して、手術の前後からリハビリテーションを開始します。安全確実に行えるよう、また訓練により向上した能力を生活面で十分に活かしていけるよう、各スタッフが密な協力体制をとっています。
呼吸器リハビリテーションチーム
以下のような疾患のリハビリテーションを実施します。
- 間質性肺炎
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の急性増悪
- 市中肺炎
- 誤嚥性肺炎
- 胸部・腹部手術後
呼吸状態をみながら運動を行い、日常生活上の制限が生じないようにすすめています。
間質性肺炎の安定期や急性増悪に対するリハビリテーションを積極的に行っています。
がんリハビリテーション
がんと診断された方の、様々な”病期(予防・回復・維持・緩和)“に応じたリハビリテーションを行い、日常生活や療養をサポートします。
外来がん治療センターにおいても、運動や日常生活活動(ADL)の相談を受けております。
心臓リハビリテーションチーム
緊急入院した急性心筋梗塞などの患者さんに対して、検査・治療と併行して心臓リハビリテーションが開始されます。医師や看護師など多職種からなるチームで、入院中の運動療法のみだけでなく、二次予防に向けた包括的なリハビリテーションを提供します。
また、心臓の手術を受けた患者さんにも、術後早期からリハビリテーションを開始します。安全かつ早期の身体機能向上を図るとともに、できるだけ早い社会復帰を目指します。
言語聴覚療法
失語症・高次脳機能障害・構音障害注1・摂食嚥下機能障害注2などが対象となります。各センターからの依頼に応じ、さまざまな専門分野のスタッフが協同して治療にあたります。特に摂食嚥下機能障害については、栄養サポートチームと連携して、早期から栄養管理を実施します。 また、各種検査によって症状を把握した上で、患者さんへのコミュニケーション方法についてご家族やスタッフに指導・助言を行います。
(注1)構音障害:うまく言葉を喋ることができない障害
(注2)摂食嚥下機能障害:うまく飲んだり食べたりすることができない障害